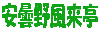
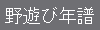
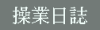
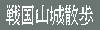
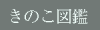
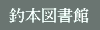
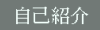
風来亭のフォト日誌
松本市・平瀬城跡

武田勢が攻め落として204人を打ち取ったと高白斉記にある平瀬城。
松本から小笠原方を駆逐し安曇野侵攻を企図する信玄にとってはどうしても抜かねばならない要衝の地だったが、
平瀬城の場所については二説あって定かではない。
犀川右岸に流れ込む犀乗沢を挟む尾根上にある山城か、奈良井川左岸の丘陵上の川合鶴宮八幡宮の場所だとの二説。
どちらの説に与すべきか、自分なりに検証してみようと犀乗沢の山城に登った。

犀乗沢筋の道を10分ほど遡上、左側斜面に取りつけられた細い山道を登り始めるとすぐに
遺構と思われる郭状の削平地が左右に展開する。とりわけ左側の木立に垣間見える郭が見事。
さらに登ること10分たらずで本郭。
本郭からは松本平から安曇野にかけて一望できる。生憎の曇り空のためアルプスの眺望は得られないものの
梓川と奈良井川が合流し犀川と名を変える河の流れが足下にある。
別説で平井城跡とされる川合鶴宮八幡宮の社叢も見える。

双方の説の現場を訪れてみたが、どちらの説に賛同できるか印象的にも結論を得ることはできなかった。
八幡宮説について、武田の大軍が接近しつつあったにも関わらず、
山城に立て籠もらずにあえて平城で迎え打ったことに疑問が残った。
本郭跡の老杉の前の石塚に建立された鎮魂の碑が印象的だった。
犀乗沢を挟んで南側にある支城には踏み跡さえ発見できなかったので、
探索がてら穏やかな初冬の日に支再び訪れてみたい。安曇野と北アルプスの絶好の展望台。
古代以降この地を領有し統轄してきた平瀬氏は鎌倉幕府滅亡後に信府に入る。
信濃守護小笠原氏の信任あつく南北朝争乱時や、平時の生活においても表裏一体の関係で運命を共にしてくる。
平瀬は小笠原氏にとって、その後も最も重要な拠点の一つであったことが知れる。
おそらく平瀬城は南方の犬甘城と共に林城に前後する室町期に相互必要あって築城されたものと考えられる。
平瀬城は北の本城、南の支城とから成っている。
後年天文20年(1552年)10月24日武田晴信の猛攻に会い落城、
その際平瀬方武将204人が生命をおとしている。
武田方により同城は同年10月28日に城割そして鍬立がなされた。
平瀬城(北・本城)
山田地籍の北部よりほぼ西方へ派生する尾根の先端部分に主要遺構をおく標高約716m前後比高差約140mで、南、西、北の三方は落差の激しい重崖状を示し自然要害の地選(じより)条件を具備している。現在遺構の残存状態はよく、大手道を行くと道をたちきる竪堀、道の両沿いにおびただしい帯曲輪、虎口、武者走り、主郭、二の郭、土塁や石垣の一部、馬出し、尾根をたちきる堀切、厳重な急な山の斜面を刻む収斂形の竪堀群、あるいは散開形の竪堀などの施設を認める。
この本城の各所より焼米、石臼内耳土器などの破片出土をみており、戦時における朗城の足跡をうかがわせる。
平瀬城(南・支城)
山田地籍の高山嵐から西方へ更に曲折して西北方へ下る尾根筋の先端部分に遺構は残存する。
やはり西・北・東の三方は垂崖状となり要害の地に立っている。
標高は約650m比高差約80mで犀乗沢をはさみ北の本城をあおぎみる位置にある。
南支城の遺構残存状態もよく主郭には南西北の三方に土塁が残存し虎口を北にとりその前面に二の郭をおいている。
主郭の東下に腰曲輪が4面連続し南の尾根に堀切が4連続、西斜面は竪堀が3条、東斜面は収斂形の竪堀群を認める。